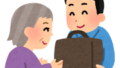📌 この記事でわかること
✅訪問診療とはどんなサービスか?
✅訪問診療と訪問看護の違いは?
✅訪問診療を受けるための条件と流れ
✅訪問診療が必要になるケース(具体例付き)
✅訪問看護・訪問リハビリとの組み合わせ方
🔹 訪問診療とは?どんなサービス?
📌 訪問診療とは、「通院が困難な人」のために、医師が定期的に自宅を訪問し、診察を行う仕組みです!
📌 訪問看護とは異なり、「医師が診察を行う」ことが大きな特徴です!
🔹 訪問診療と訪問看護の違い
| 項目 | 訪問診療 | 訪問看護 |
| 提供者 | 医師 | 看護師・リハビリ専門職 |
| 目的 | 定期的な診察・処方・病状管理 | 医療的ケア・リハビリ・健康管理 |
| 対象者 | 通院が困難な人 | 在宅で医療的支援が必要な人 |
| 保険適用 | 医療保険のみ | 医療保険 or 介護保険 |
📌 訪問診療は「定期的に医師の診察を受けるサービス」、訪問看護は「医療処置や健康管理をサポートするサービス」!
📌 基本的に、訪問診療と訪問看護は併用できる場合が多い
🔹 訪問診療を受けるための条件と流れ
📌 訪問診療は「医師の判断」が必要であり、自分の希望だけで自由に利用できるわけではありません!
📌 そのため、訪問診療が必要であることを「正しく伝える力」が重要になります!
📌 訪問診療を受けるための条件
✅ 定期的な診察が必要で、通院が困難な人(寝たきり・重度障害など)
✅ 主治医が「訪問診療が適している」と判断した場合のみ利用可能
✅ 訪問診療を行う医療機関と契約を結ぶ必要がある
📌 訪問診療は「通院が難しい人」に対する支援のため、誰でも利用できるわけではない点に注意!
📌 訪問診療を希望する場合は、まず主治医やケアマネージャーに相談し、医師の判断を仰ぐことが必要!
🔹 訪問診療を利用するきっかけ(具体例付き)
📌 訪問診療を受けるきっかけは、「通院の負担が大きくなった」「自宅で医療管理が必要になった」など様々です!
| ケース | 訪問診療を検討するタイミング | 訪問診療を導入する理由 |
| ケース①:高齢で外出が困難になってきた | 「病院に行くのが大変になり、家族の付き添いなしでは通院が難しい」 | 定期的な診察・薬の処方を受けるために訪問診療を導入! |
| ケース②:認知症が進行し、通院時の負担が大きい | 「通院のたびに混乱し、待ち時間が負担になっている」 | 自宅で診察を受けることで、環境変化による混乱を防ぎ、安心して治療を継続! |
| ケース③:退院後の病状管理が必要(心不全・慢性疾患など) | 「入院は終わったが、病状が不安定で、定期的な経過観察が必要」 | 病院と同じように医師の診察を受けながら、自宅療養が可能に! |
📌 訪問診療は、「通院が難しい」「自宅で医療的なサポートを受けたい」と感じたときに検討すべき選択肢!
📌 医師やケアマネの提案を待っているだけでは必要なサービスに繋がらないこともある!
📌 デメリットとして、緊急時・急変時等で対応が遅れる場合があることを知っておく!
🔹 訪問診療と訪問看護・訪問リハビリの関係性
📌 訪問診療は「診察・治療」を目的とし、訪問看護や訪問リハビリと併用することで、より包括的な在宅医療が実現します!
| 利用者の状態 | 訪問診療の役割 | 訪問看護の役割 | 訪問リハビリの役割 |
| 脳梗塞後の自宅療養(要介護3) | 定期的な診察・薬の処方(血圧管理・脳梗塞後の再発予防) | 服薬管理・血圧測定・医療処置(褥瘡ケア) | 歩行訓練・筋力維持のためのリハビリ支援 |
📌 上記表の併用例は訪問診療が「診察・治療の指示」を出し、訪問看護や訪問リハビリが「日常のケア・機能維持」をサポートする関係!
🔹 まとめ&次に読むべき記事
✅訪問診療は「通院が難しい人」が定期的に医師の診察を受ける仕組み!
✅訪問診療は「医師の判断」で利用可否が決まるため、必要性を正しく伝えることが重要!
✅訪問診療を受けるきっかけは、「通院の負担」や「自宅での医療管理が必要」など様々
!
📖 次に読むべき記事
➡第16回:ショートステイの上手な使い方!一時的に預ける介護サービスとは?
・在宅介護の負担を軽減する方法
・スムーズに活用するためのポイント
介護保険の申請をスムーズに進めるための考え方について、こちらの記事で詳しく解説しています。
🔹 著者情報
📌 この記事を書いた人
- 社会福祉士 / 居宅介護支援専門員
- 居宅介護支援事業所・通所介護事業所を経営
- 介護保険申請の難しさを感じ、ブログを通じて情報発信中
🔗 公式情報
📌 介護保険制度の詳細は、厚生労働省の公式ページをご確認ください。
➡ 厚生労働省 介護保険制度