📌 この記事でわかること
✅ 介護認定のために行われる「訪問調査」とは?
✅ 調査で聞かれる主な内容と、伝え方のポイント
✅ 適切な介護認定を受けるための注意点
🔹 訪問調査とは?どんな目的があるの?
📌 訪問調査とは、要介護認定を受けるために行われる面談のこと です。
📌 申請者の生活状況や身体の状態を確認し、どの程度の介護が必要かを判断するための重要なステップです。
訪問調査の流れ
- 申請後、市区町村から委託された調査員が自宅を訪問
- 本人や家族と面談し、日常生活の状況を聞き取り
- 介護の必要度を判断するための「74項目の調査」を実施
📌 この調査結果は、主治医の意見書と合わせて審査され、「要介護度」が決定します。
📌 調査の受け答え次第で、本当に必要な支援が受けられないケースもある ため、正確に伝えることが重要です!
🔹 訪問調査はどのように進む?
訪問調査では、調査員が 決められた調査項目 に沿って質問を行い、利用者の状態を記録します。
大まかに、以下のような流れで進みます。 また、調査時に困っていることを適切に伝えないと、本来受けられる支援が制限される可能性があるので注意しましょう。
📌 訪問調査の流れ
① 挨拶・本人確認
② 質問による聞き取り調査(基本チェック項目)
③ 動作確認(立ち上がりや歩行など)
④ 家族や同居者からの補足情報のヒアリング
⑤ 書類確認・終了
🔹 訪問調査ではどんな質問をされるの?
訪問調査では、生活のあらゆる側面に関する質問を受けます。
📌 主な調査項目
| 質問の内容 | 具体例 | 参考回答例 |
| 日常生活動作(ADL) | 「自分でトイレに行けますか?」 「食事は自分でできますか?」 | 「日中はなんとか行けますが、夜は間に合わないことがあります」 「食べることはできますが、箸やスプーンを落としたり、時間がかかることが増えました」 |
| 認知機能の確認 | 「今日が何月何日かわかりますか?」 「最近の出来事を思い出せますか?」 | 「カレンダーを見ればわかりますが、何も見ないとすぐには思い出せません」 「昨日のことは覚えていますが、一週間前のことはあまり思い出せません」 |
| 医療的な管理の有無 | 「定期的な服薬はありますか?」 「医療機器(酸素・カテーテルなど)を使用していますか?」 | 「1日3回薬を飲んでいますが、飲み忘れることがあります」 「酸素を使っていますが、装着したままだと動きにくいので外してしまうことがあります」 |
| 家族のサポート状況 | 「日中は誰が介護をしていますか?」 「外出時の付き添いは必要ですか?」 | 「家族が仕事でいないので、基本的に一人で過ごしています」 「近所のコンビニくらいなら一人で行けますが、病院やスーパーには付き添いがないと厳しいです」 |
🔹 訪問調査の注意点と対策
訪問調査で適切な認定を受けるためには、以下の点に気をつけましょう。
📌 訪問調査のポイント(※家族は出来るだけ同伴したほうがよい)
✅ 無理をしないで普段どおりの姿を見せる!
✅ 家族が同席するとスムーズ(本人が説明しづらい場合代わりに家族が回答できる)
✅ 事前に困っていることをメモ、画像、動画で記録しておくと安心!
✅ 「本人が無意識に『できる』と言ってしまうのを家族が同席すると防げる」
✅ 調査員の質問に「はい/いいえ」だけでなく、詳細を説明する
例:「デイサービスに通っているが、送迎がないと通えない」
✅ できる・できないの二択ではなく、「どのくらいの頻度で困るか」を伝える
例:「歩けるけど、長い距離は歩けない」「食事はできるが、こぼしてしまう」
✅ 普段の生活の困りごとを正直に伝える
例:「夜間のトイレで転倒しそうになる」「薬を忘れてしまうことが多い」
📌 訪問調査は、「普段の生活の様子」 を伝える場です!
📌 「頑張ればできる」ではなく、「どんなサポートがあれば安全か?」を考えながら説明すると、より適切な認定につながります。
※下記語りまとめは、介護保険申請後の「訪問調査で聞かれること」を想定した文例です。
実際に申請していなくても、生活の中で支援が必要になってきたと感じている方に参考になる内容です。
母は現在、介護保険のサービスは利用していませんが、生活の中で支援が必要になりつつあると感じています。歩行時にふらつきがあり、台所から部屋に戻るだけでも壁や家具につかまって移動しています。入浴は一人で行っていますが、足を上げる動作がつらくなってきており、頻度も減ってきました。トイレは自立していますが、夜間に失敗することがあり、衣類の処理や声かけが必要になることがあります。認知面では、時間の感覚があいまいになっていて、夜中に活動したり、同じ話を何度も繰り返すことがあります。
今は家族で見守っていますが、在宅での生活を続けるには、今後何らかの支援が必要になると考えています。
調査では「できるかどうか」だけでなく、「できていても手間や不安があるか」が大切にされます。この文例のように、「日常の中でどの場面が負担になっているか」を整理しておくと、支援につながる可能性が高まります。
🔹 訪問調査で気をつけたいポイント
訪問調査では、「調査員の視点」を意識すること も大切です。調査員は以下のような点をチェックしています。
✅ 訪問調査のチェックポイント
- 日常生活でどの程度サポートが必要か?
- 本人の訴えと家族の意見に食い違いはないか?
- 環境や家族のサポートで生活が成り立っているか?
📌 たとえば、「一人でトイレに行ける」と答えても、「家族が支えているからできている」 というケースもあります。
📌 家族がどのくらい手助けしているか?も正しく伝えることが重要 です!
🔹 訪問調査の結果を待つ間にできること
訪問調査が終わると、審査を経て 「要介護度」 が決まります。
結果が出るまでの期間(約30日間)、以下のことを準備しておくとスムーズです。
✅ 要介護度が出た後に備えて、準備しておくこと
- 住んでいる地域のケアマネージャーを把握しておく
- 住んでいる地域の介護サービスの種類を調べておく
- 住んでいる地域の支援制度を確認しておく
📌 認定結果が出たら、すぐにサービスを利用できるよう、下記URLから自分の住んでいる場所にある社会資源の把握等次のステップの準備 を進めておくと安心です!
社会資源把握:介護事業所・生活関連情報検索「介護サービス情報公表システム」
🔹 まとめ & 次に読むべき記事
📌 この記事のまとめ
✅ 訪問調査は、要介護認定を決める重要な面談! ・生活状況を正しく伝えることで、適切な介護度を得ることができる
・調査員は「本人の状態」「家族のサポート」「環境」を総合的に評価
✅ 訪問調査のポイントを押さえて、正しく伝えることが重要! ・できる・できないではなく、「どのくらいの頻度で困るか」を伝える
・「頑張ればできる」ではなく、日常のリアルな困りごとを説明
・家族の支援の有無も正しく伝える
📖 次に読むべき記事
➡ 「主治医の意見書ってどうやって書かれるの?」(第4回)
・訪問調査と並行して提出される「主治医の意見書」の役割とは?
・どんなポイントが書かれているの?
・意見書の内容は介護認定にどう影響するのか?
介護保険の申請をスムーズに進めるための考え方について、こちらの記事で詳しく解説しています。
🔹 著者情報
📌 この記事を書いた人
- 社会福祉士 / 居宅介護支援専門員
- 居宅介護支援事業所・通所介護事業所を経営
- 介護保険申請の難しさを感じ、ブログを通じて情報発信中
🔗 公式情報
📌 介護保険制度の詳細は、厚生労働省の公式ページをご確認ください。
➡ 厚生労働省 介護保険制度

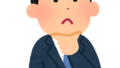

コメント